「チュンチュンチュン」お手本のような鳥のさえずりが聞こえる。
カーテンの隙間から薄く伸ばされた日差しは、かろうじてまぶたの裏側にまで届き、小さく揺れている。
二人分の体温で温められた布団の中は、この世の心地よさをすべて集めても敵わないだろう。
隣で寝ている夫の小さな寝息と上下する布団に、たしかに私の隣りにいてくれていることを実感する。
『こんな幸せがあって良いの?このままずっと寝ていたい。』
再び意識が消え入りそうな中、頭の中から電話の音が聞こえてきた。
***
プルルルルループルルルルル…
「はい、はい!」濡れた手を拭きながら、iphoneに向かって話しかける。
ちょうど食器を洗いはじめたところでの電話。
滅多に鳴ることがない電話の着信音が鳴るときは、いつもタイミングが良すぎる。
私が作業をはじめるのを待っているのだろう。
テーブルの角に置かれているiphoneを取り上げ、邪魔者が誰かを確認する。
”お母さん”
自然と背筋が伸び、見えていないのにエプロンを整え電話に出る準備をする。
実の母は”ママ”で登録しているから、”お母さん”と表記されるのはもう一人の母しかいない。
隆のお母様、陽子さんからの電話だ。
「もしもし、橘です。」いまだに慣れない精一杯のよそ行きの声で電話に出る。
「こんにちは、美穂さん。お久しぶり。いまお電話いいかしら?」
いつもと変わらない優しい声。陽子さんの声は不思議と周りを落ち着かせる。
通り過ぎていく時間はゆっくりと感じられ、小さな子どもに袖をつかまれて、歩くペースを合わせる感覚に似ている。
**
まだ結婚する前、橘家に私が加わる形で旅行に行ったことがある。
長男の隆が運転する車に、陽子さん、お父さんの誠さん、妹さんの舞さん、私を加えた五人での家族旅行だった。
「小仏トンネルを先頭に、約20kmの渋滞です。」
カーナビから流れる交通状況に、「これはなかなかの渋滞だね。覚悟しないと!」なんて明るく話していた頃が懐かしい。
おおらかな人が多い橘家でも、全く進まない渋滞を目の前にしたら、やはりイライラするのだ。
段々とハンドルを叩く人差し指のペースが早まっていく隆の姿に、まだ知らなかった”人間”を見た気がして、少し嬉しかった。
みんなの口数も減り、車の中の空気は外の天気とは裏腹に、曇天へと変わっていく。
誰かが何かをするわけでもない。
誰かが何かを言うわけでもない。
ただただ、一人ひとりからでるマイナスの体温が、車の空気を冷やしていった。
「たっぷり時間が使えることは、贅沢なことね。」
陽子さんの一言だった。
『早くゴールしたい!』という意味もないレースをしていた皆の気持ちが、ゆっくりと景色を見ながら楽しむ散歩へと変わっていった。
**
「はい!ちょうど手が空いたところで。」
「そう?良かった。美穂さん元気に過ごせている?隆になにか言われたらすぐに言うのよ。」
「はい!いつもお気遣いありがとうございます。」
「楽しいのよ、美穂さんとお話できて。遠慮なく連絡ちょうだいね。」
「はい!それで、今日はなにか御用が?」
「そうそう。来週の土曜日に私だけでお邪魔しようかと思って。前の日が結婚記念日じゃない?」
「はい!覚えていてくれてたのですね。」
「私に素敵な娘がもうひとりできた特別な日ですもの。忘れるわけないでしょ?」
「はい!ありがとうございます。土曜日なら二人とも家にいるので是非お越しください。」
「ありがとう。お祝い持ってお昼過ぎに伺うわ。隆によろしく伝えておいて。」
「はい!楽しみにしています。」
「それじゃあ、よろしくね。」
「はい!失礼します。」
***
「それじゃあ、よろしくね。」-「…ゃあ、よろしくね。」-「…、よろしくね。」-「…くね。」
頭の中でお母さんの声がリフレインされている。
そっと目を開けると、遠くにモンステラが見える。最近若葉をつけ、薄緑がカワイイ。
視線を手前に寄せると、テーブルの上に歴史を感じさせる深緑のワインボトルが見える。
空のワインボトルに日が当たると、よりその深さを際立たせていた。
ワインボトルを囲むように、仲良く並んだワイングラスや二人で食べたケーキの箱が見える。
『そうだ。昨日は結婚記念日だったんだ。』
今までの思い出を語り合い、他愛もない話で盛り上がり、未来について想像を膨らませた。
幸せな時間を二人で過ごし、そのまま眠りについんだ。
充電コードを掴んで手元にiphoneを手繰り寄せ、今の時刻を確認する。
”9:58”
二度見する余裕すらなかった。
「隆大変!」
「ん?どうした?」伸びをしながら隆が応える。
「これ見て!」持っていたiphoneを隆の目の前に突き出した。
どんどんと青ざめていく隆の表情で、伝えたいことはすべて伝わったと確信する。
「何が一番時間かかる?」こういう時に冷静に行動できる隆はカッコいい。さすが、私の選んだパートナーだ。
「料理。」返答も最小限になっていく。
「じゃあ、美穂は料理。僕は片付け。いい?」隆隊長の指示は端的だ。
「隊長!」中指までピンと伸ばし、右手を天井へと突き上げ進言の許可を得る。
「美穂隊員。なんだね?」
「この時間で充分な料理は私だけでは用意できません!」
「なにかアイデアはあるのかね?」
「Uber Eatsはいかがでしょうか?」
「採用!」
手分けして作業を進めながら注文可能なイタリアンを二人で探し、注文が完了したのは”11:20”。
到着予定時刻は”11:50”。
ぎりぎり間に合う。陽子さんの「お昼過ぎは、”12:00”ピッタリを意味する。」
残り30分。後3品ほどは作れそう。寝坊は取り返せた。
★★★
11:20
「ごめんね!この時期は週5のお仕事お願いできなさそうで。週2日で組んでるから、よろしく!」
こう言い渡されてから約1ヶ月が経っている。
あんなにも心のこもっていない『ごめんね!』は、初めてだった。
とはいえ、やめるわけにも行かずまだ週2日の付き合いは続いている。
それでも勿論生きるためには別の稼ぎを探さなければいけない。
そんな時にテレビから流れてきたのが”Uber Eats”のドキュメンタリーだった。
「配達員の方に安心してもらえるように。」
「安全に、快適に運べるように。」
僕の求めているものがそこにあるような気がして、気づけば登録を済ませていた。
どこかに出向く必要はなく、全てオンラインでの登録にも驚いたが、バックまでアマゾンで購入だったのは少し笑ってしまった。
緊張で手汗をかきまくった初めての配達から約1ヶ月。今ではUber Eatsの配達員が日課になっている。
配達員を初めて1ヶ月と1日の今日。無意識にはじめた日のことを思い出していた。
ちょっとセンチメンタルな気持ちに浸りながらわざとらしく空を見上げると、Uberのアプリから配達の指示が届き、現実へと引き戻される。
「あのイタリア料理屋か。」
行き先を確認しながらこぼれる独り言も、今では配達とセットだ。
料理をピックアップして、届け終わるまでに30分ほど。
平均的な時間だし、レストランも届け先のマンションも行ったことがある場所だ。
すっかり慣れた動作でリュックを背負い、自転車にまたがり出発する。
11:25
イタリアレストランに到着。
土曜のお昼時だからだろうか。店内のテーブルはほとんど埋まり、まだ食事を指定ない人の姿も目に入る。
「ウーバーです。」
入ってすぐのところにいる店員のお姉さんに声をかける。
「あ、はい。少しお待ち下さい!」
何回か受け取りに来ているから顔なじみになっていて、待っている間少し話しもするくらいの仲にはなっていたけれど、今日の対応はどこかよそよそしい。というか、余裕がないのだろう。
厨房へ確認に行った後ろ姿を見ながら、そんなことを推理していた。
手ぶらで戻ってきた彼女は、「今作っているので、もう少し待っていてください。」と申し訳無さそうに言ってくる。
こちらは特別急いでいるわけでもないし、極端な話、10分、15分遅れても目くじらを立てて怒るお客さんに会ったことはない。そもそも、本業(今ではどっちが本業か分からないけど…)ではクレーム対応は上司ではなく僕がやらされていたから、怒られても何も感じないし、切り抜け方も知っているつもりだ。
「あ、全然大丈夫です。忙しいですね。」
「はい。おかげさまで。」そう言い残し、また奥へと吸い込まれていく。
楽しそうに食事をするお客さんの姿を見ていると、『笑顔を作るのは楽じゃない』そんな言葉が浮かんでくる。
11:28
「お待たせしました!」
頬からはまだ、忙しさがにじみ出ているが、目からは精一杯の笑顔が伝わってくる。
『やっぱり彼女は優しい人だ。』僕の中で確認のスタンプが押される。
中身を確認しながら小さな両手に持たれていた袋を一つずつ受け取ると、主張の激しいUber Eatsのリュックへと入れ込んでいく。
11:30
「お願いします!」
背中を押す彼女の声もリュックに入れて背負いながら、再び自転車へとまたがり届け先のマンションへと出発だ!
11:45
勝手知ったる道。
彼女の優しさがエンジンブーストとなって、少し遅れていた配達時間もすっかり取り戻していた。
バケツに一滴落としたような薄く広がった青色に、すっと一本の飛行機雲が走っていく。
そばにはハート型にも見える雲が気持ちよさそうに浮かび、キャンバスに物語を描いている。
「すみませーん!ここから先は通行止めです!!」
遠くからおじさんの声が聞こえる。姿は見えないけど、おじさんだと分かるから不思議だ。
全体的に痩せ型で、日焼けした肌は歴史を感じさせる焦げ茶色だろう。
目は少し垂れていて細く、鼻は大きく、唇は薄い。
剃り残して伸びてきている髭は白髪がまじり、肌の色とのコントラストで際立って見えている。
そんな姿を想像しながら、目的地のマンションへと進むと、クイズ番組の正解発表前のBGMのように工事の音とおじさんの声が近づいてくる。
この角を曲がれば、後は一直線で目的地のマンションへと到着する。
嫌な予感を胸に角を曲がると、そこには想像通りのおじさんが立っていた。
『大正解だ!!』
100万円ぐらいの賞金を出してほしいところだが、そんなことも言っていられない。
少し遠回りになるが、別の道を進むしかなさそうだ。
「この道を進めないとなると、どこから行ったら良いのかしら?」
「いやぁー、ちょっと、たまたま工事できているだけなので、分からないですね。」
「そうなの。それは困ったわね…」
クイズの正解だったおじさんと、大きめの風呂敷とワインが入っていそうな紙袋をもった五十代半ばの女性が話をしている。
昨日はやっていなかった工事だ。あのおじさんは、おばさんのクイズには答えられないだろう。
「どうかしましたか?」
二人の間に入って声をかける。
普通にしていても大きいだろう。真ん丸の目を更に大きく見開いてこちらを向いた女性の顔は、顔の半分以上を2つの瞳で創り上げられているようだった。
「あら、優しいお兄さん。ありがとう。実はね、この先のマンションへ行きたいのだけれど、道がわからなくて。」
はじめから関わりがなかったかのように、おじさんはいつも通りの交通整理へと戻っている。
「これから行くところなので、案内しましょうか?」
「有り難いけど、お兄さんはお仕事中でしょ?」目線は背中のリュックに向いている。
「仕事は責任を持ってやりきらないとね。よろしければ道だけ教えていただければひとりで行けるわ。」
『世界をゆるやかに優しくしてくれる人だ』
初めて会った人だけど、なぜだか確信が持てる。
「それじゃあ、難しくないので説明しますね。」持っていたiphoneにGoogle MAPを映し出し、航空写真で道案内をする。
「今日はパーティーか何かですか?」
「そうなの。ちょっとしたお祝いでね。」
「もしお時間あるなら、美味しいケーキ屋さんがあるので一緒にご案内しますよ。」
「あらそうなの!それは良いことを聞いたわ。ぜひ教えて。」
3日前に初めて受け取りに行ったケーキ屋を案内する。
”街の小さなケーキ屋さん”といった佇まいだったが、ショーケース越しでもケーキ一つ一つが丁寧に作られていることが伝わってきた。普段甘いものはあまり食べないが、気になりすぎて配達後に戻ってきて買ってしまったほどだ。
生クリームが甘さ控えめで口に入れた瞬間に溶けていき、いくらでも食べれてしまう。今まで知らなかったことが悔やまれる。
記憶が新しかったせいかもしれないし、このマダム(語彙力はないけどこの表現が合っている気がする)があまりにも素敵だったからかもしれないけど、『あの美味しさを知ってほしい!』と気づけばオススメしていた。
「プラス5分ぐらいにはなりますが、そんなに遠くないので。」
そう言いながら、ケーキ屋からマンションに向かう道を改めて説明する。
「ありがとう。お名前を伺ってもよろしい?」
「一真です。川口一真です。」
「カワグチカズマさん。ありがとう。通れない道があることも悪くはないものね。」
「こちらこそ、有難うございます!」
「あなたがお礼を言うなんて、少し変よ。でも、嬉しいわ。」
少し下を向きながら上品に微笑む姿に見とれてしまう。
「気をつけて、いってらっしゃい。」
リュックの中身が更に一つ増えた気がした。
11:55
「すみません。遅くなりました。Uber Eatsです。」
「待ってましたぁ〜。今開けますね!」
銀色の無機質なスピーカーから、生気に満ちた声が聞こえる。さながら、試合後のインタビューのようだ。
エレベーターで目的の階まで上がり、扉の前で呼び鈴を鳴らす。
首筋を通り抜ける風が心地よい。
「は〜い!」という声ともに扉が開くと、髪を後ろで一本に結んだエプロン姿の女性が立っている。
なぜだか充実感に溢れた表情をしている女性は、
「ありがとうございます!今日から工事始まったみたいで、道、大変じゃなかったですか?」
と声をかけてくる。
配達員に声をかける人は天然記念物なみに少ないので少し面食らうが、接客はお手の物、
「はい。調べておけばよかったのですが捕まってしまって。遅くなりました。」
そう言いながら頭を下げる。
「あ、ごめんなさい!そういう意味じゃなかったの。お疲れさまでした。」
かすかに聞こえるエプロンがこすれる音に、目の前の女性も頭を下げている姿が映し出される。
再び聞こえた音をまって顔を上げると、目の前の女性はこちらを見て微笑んでいた。
「ありがとうございました!」
もう一度頭を下げ、配達先を後にする。
「お気をつけて。」空になったはずのリュックの中にはまだ3つ、僕だけの荷物が残っていた。
★★★
”ピンポーン!”
モニターホンからチャイムが鳴る。
そこに映し出されているのは陽子さんの姿だ。
「お母さん、こんにちは。今お迎えに行きますね!」
「美穂さん、こんにちは。初めてじゃないから大丈夫よ。」
「ありがとうございます。」
そう言いながらオートロックを解除する。
「エレベーター前まで迎えに行ってくるよ。」
後ろに立っていた隆が玄関へと向かいながら声をけてくる。
「ありがとう。」こういう時にそっと気遣える隆はカッコいい。さすが、私の選んだパートナーだ。
「お邪魔します。」
「お母さん、今日はありがとうございます。」
「これ、母さんからのお土産。」隆の手には3つも手土産がぶら下がっている。
「こんなに沢山!?重かったでしょう?」
「二人の記念日のお祝いなんだから、重さなんて感じないわ。それに素敵な出会いがあったんだから。」
フフフッと微笑む陽子さんに、
「なんだよ。素敵な出会いって?」と手土産をテーブルに運びながら隆が問いかける。
「そのケーキに纏わる話。後でお話するわ。」
「もったいぶって。親父にヤキモチ妬かれるぞ!」
橘家の家族になれて本当に良かったと思う。
昨日話した未来についての想像が、確かにこの世界にはありそう。
Uber Eats
2021.03.16
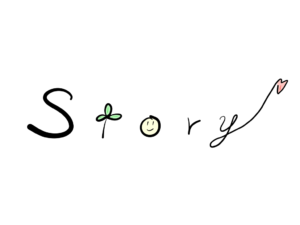
コメント