「翔。来週末母さんと旅行に行くけど、久しぶりに一緒にどうだ?」
テレビからクイズ番組のオトボケ回答だけが聞こえてくる食卓で、久しぶりに聞こえた父からの肉声だった。
「ほら、覚えてない?子供の頃家族三人で行ったじゃない。翔が沢山写真を撮ってくれたところよ。」
母の問いかけに、いつも通り、『いいよ。二人で楽しんできなよ。』と返答しているつもりだった。
でも、実際にはその声はテレビの正解を伝える音声を邪魔することなく、細い糸で僕の中に手繰り寄せられるように、そっとそっと沈んでいった。
***
「翔は助手席が良いか?」
「うん!パパの隣に座る!ママは後ろね!」
「はい。翔が、ちゃんとパパのナビしてあげるのよ。」
「任せて!」
買ったばかりのトヨタのカローラフィールダーに家族3三人で乗り込み、恒例の旅行へと出かける。
自分で言うのも何だが、小学1年生の僕は、純粋無垢で可愛かったと思う。
父は運転好きで、2年に1回くらいのペースで車を買い替えていただろうか。
5月の後半から6月の頭頃に、営業のサカタさんがうちにやってきては、3〜4種類のカタログをテーブルに並べて父と楽しげに車の性能や新しい装備について話していた。
父が少し見下ろす格好になるぐらいソファーが沈み込むサカタさんの姿と、『なんで、CMに出ないんだろう?』と子供ながらに思うほど、美味しそうに麦茶を飲み干す姿が強く印象に残っている。
話はよくわからなかった。だけど、大の男二人が楽しそうに話している世界に漠然と憧れ、テーブルの上に広がるカタログを見ては二人の話が分かる”フリ”をしていた。
きっと楽しそうに聞いていたのだろう。よくサカタさんは僕を膝に乗せてくれて、カタログを見せながら、「排気量がどうとか」、「ステアリングがどうとか」、「アクセルの踏み心地がどうとか」を話してくれていた。何がなんだか全然分かっていなかったけど、”ウンウン”とうなずきながら話を聞いていた。
大人の世界に触れるのは、それだけで魅力的だったのだと思う。
そして、大抵この”サカタ会議”(確か小学校3年生の時に勝手に名付けたと思う。)の1ヶ月後に、うちに新しい車がやってきていた。
「さて、今回の車はどうかな?」
わざわざハンドルの右側に顔を突っ込んで、回る鍵とエンジンがかかる音の合唱を楽しむように、父が鍵を回す。
ハンドル越しに見える父の顔は子供の僕でも分かる、僕以上の子供顔だった。
”クッカッカッカッカッ、ブルーン”
決して大きくない、控えめなエンジン音が車内にも届き、より一層父の口角が上がる。
「それじゃあ、出発!」
コレも、恒例になっている父の合図だ。そして、この後決まって行われるのは、
”パチパチパチパチ!!”
僕と母からの拍手だった。
子供の頃の僕にとっては、この瞬間はワクワクが抑えきれず、拍手とともに足もバタバタさせていた。
とにかく父の運転で遠くに行けることが嬉しかったし、行ったことがない場所というだけで冒険に出る感覚だった。それに、何より家族でずっと一緒に過ごせる時間が好きだったのだと思う。
旅行に行くときのおなじみの道。高速道路へと続く道の景色が通り過ぎていくたびに、僕のワクワクは増えていった。
当たり前になり始めていたETC専用ゲートを通り、窓越しに見える景色が線へと変わっていく映像に宇宙船のワープを重ね、『僕たちはどこへでも行けるんだ!』と想いを世界に飛ばしていた。
ただ、子供の体力は長続きしないから、前日の寝不足も相まって、次見る景色は大抵サービスエリアに綺麗に収まる色とりどりの車たちだった。
車でのほとんどの時間を寝て過ごしていたのに、旅行の思い出の中に車での出来事がかなり強く刻まれているから不思議に思う。
家族だけの空間だから?
父親の運転に身を預けているから?
限られた空間の中で力を合わせて楽しい時間を作っていたから?
何が原因だったかは未だにわからないけど、”車の中”という空間は、僕にとって特別なものだった。
目的地についた日は、ホテルで過ごし翌日の作戦会議をするのが通例だった。
確か、いくつかの教会と滝、旧商店街を回ることにしたんだと思う。他に行った場所があったかもしれないけど、もう覚えてない。
作戦会議をした後に父とお風呂に入り、『大人の体はすごいな…』と思っていた。
出てくる母を待つ時間は、父にジュースを買ってもらえるお楽しみの時間で、小学3年生の旅行で初めてコーヒー牛乳を飲めたのは今でも鮮明に覚えている。瓶に入った、甘々でコーヒーは殆ど入っていないであろうコーヒー牛乳だったけど、大人の階段を一段登った日だった。
翌日は1日かけて昨日立てた作戦を実行していく日。
どの順番で回るのが効率的なのか、一つでも多く回れるルートはどうか、そんなことをみんなで話しながら一つ一つ回っていく。父が運転し、母がガイドする中、僕がこの旅行で任された役割は、”撮影係”だった。
「思い出を残す大切な任務。よろしくお願いします!」
父がカメラを首に掛け、僕に向かって敬礼をする。その横では母も同じポーズをしていた。
もちろん僕も敬礼で返す。
写真を撮っては父や母に見せ、褒めてもらったのを今でも鮮明に覚えている。
ホテルを出発して、はじめに到着した場所が、”石の教会”だった。
たまたまその日、その時間で結婚式をやっていて、白いドレスとタキシードを身にまとった新郎新婦が、木々の隙間からこぼれる陽の光に照らされてより一層輝いていた。
気づけばシャッターを切っていた。
『僕の想い出として残したい!』と強く思ったのだろう。
もちろん知らない二人だったし、大人になった今だったら決して撮ることは無いけれど、あの当時は純粋に自分の気持ちに正直に、残したい気持ちに従ったのだと思う。
父と母に見せると、「綺麗だね。」と褒めてくれた。
僕たちは、参列者よりも多くなっていたギャラリーの一員として、最後までセレモニーを見届け、そこにいる全員で二人の門出をお祝いしていた。
少し照れくさそうに、でも誇らしげに見える二人を、僕は最前線で撮影していた。
その日「はじめまして!」の人だらけの中、新郎新婦は嬉しそうに一人ひとりとお話をしていて、僕たちもお祝いを伝える列に加わっていた。
順番がやってくると、僕の首からカメラを取り、父が二人に写真を見せる。僕が撮った写真だ。
「とても素敵に撮ってくれたのね。」
「ありがとう。私達にとって、世界一のカメラマンよ。」
二人はかがんで僕に目線を合わせながら、プレゼントを届けてくれた。
嬉しすぎた僕は、急に人見知りが発動してしまって、静かにうなずくことしかできなかった気がする。
ずっとうつむいている僕に対して、「かわいい。」と新婦さんが頭をなでてくれた。その手の感触はまだ思い出せる。
動かなくなった僕を横目に、父と母は二人と何やら話をしていた。
後で分かったのだが、どうやら僕が撮った写真を送る約束をしていたらしい。
旅行から一ヶ月経った頃、二人から届いた手紙には感謝の言葉が綴られていて、僕の写真を飾ってくれていることを母が読んでくれた。僕は、写真が二人の元へと届いた嬉しさで家中走り回ったことを覚えている。
朝顔の種が、初めて地面を突き破って顔を出したときのような、この世界に「おはよう!」と伝えて誰かに届いたような、そんな感覚だった。
調子に乗った僕は、軽井沢の旅行中ずっと写真を撮っていたと思う。家族写真はもちろんのこと、知らない家族やグループ、外国人にも声をかけ、いっちょ前にカメラマンをやっていた。
それでもみんな、ちびっこカメラマンを受け入れてくれて、何だか沢山褒められた。
***
つい最近、Youtubeで動画を見た。
トヨタの社長、豊田章男さんの社員に向けたメッセージだ。
〜”自分”のためにプロになれ〜
プロとは、
”一芸に秀でた専門性を持っている人”
”努力を続ける人間力を持った人”
らしい。
『僕は何のプロになれるのだろう。』
自問自答してみる。
”やりたいことを見つけるため”
そんな曖昧な理由で大学へと進んだ。でも、本当のところはコレすら無いのかもしれない。
きっと、まだ”責任”と”覚悟”を持ちたくないのだろう。
『じゃあ、何をしたいの?』
すぐに答えが出るのであれば苦労はしない。
どこかで特別な自分になりたいと思っているけど、一方で特別な存在になんてなれやしないと言ってくる僕もいる。
どっちになりたいかなんて、とっくに答えは出ているのに。
自問自答している中でも動画は進んでいく。
なぜだろう。頭は考えでいっぱいになっているはずなのに、言葉の一つ一つがスッと入ってくる。
”限界は自分が決める”
”プロは自分が一番だと思っているしそうでなければいけない”
”私達マネジメントは、プロが働きたい環境を作る”
環境がプロを作るのだと思っていた。
医者の子供は医者になりそうだし、国会議員の子供も議員になるのだろう。音楽家一家は音楽家を育てるし、社長の子供は社長になるのだと相場が決まっている。
勝手に決めつけて、理由を作っていたんだと思う。失敗は怖いし、傷つきたくない。
それなら、環境のせいにしたほうがよっぽど楽だ。
だけど、プロが環境を選ぶのだ。プロなら環境を選べるのだ。
環境に選ばれるんじゃない。
『じゃあ、何がしたいの?』
**
「今回も留守番が良いの?」
母の声が、僕をいつもの食卓へと連れ戻してくれた。
「…。」
「今回は、行こうかな。」
「あらそう!三人で行けるのはいつぶりかしらね?」
僕の目を見て聞いてくる母に、「そんなこと覚えてないよ。」とそっけなく答える。
僕の返答は全く気にしていない様子で、「前行った場所にも行こうかしら?」、「アウトレットモールには行きたいわ!」とひとりで作戦会議をはじめている。
「お父さん。カメラってあるよね?」母の様子を楽しそうに見ている父に声をかける。
「あるけど、古いからな…」母から僕へと視線を移した父は、すぐさま左上、左下へと視線を変えていく。
「明日、カメラ見に行くか。予定はあるのか?」すぐに考えがまとまったのだろう。父から質問が返ってくる。
「無いよ。」
「そうか。じゃあ、ちょっと良いやつでも買っちゃうか!」
「ありがとう。」
「ちびっこカメラマンの成長が楽しみだな。」
「そんなんじゃないよ。」
テレビからは、大きなモニターに映し出された正解を見て何かを叫んでいる芸人が映し出されていた。
TOYOTA
2021.04.03
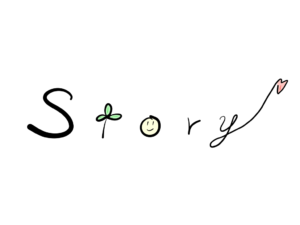
コメント