午前6時。いつものメンバーが電車に運ばれている。
端から一つ隣の席が私の定位置だ。
向かいの席の一番端に、作業着姿の50代のおじさんが座っている。
私の左隣は大きなリュックを抱えて眠っている20代の男の子がいつも座っている。
Disneyグッズをやたらとリュックにつけている女性や、教科書を熟読している女子高生、みんないつも同じ電車、同じ席に座って、同じことをしている。
電車の中の広告もいつも一緒だから、この世界だけは時間が止まっているように感じる。
その中にいる私自身もきっと、前に進めていないのだろう。
***
「チカちゃんは絵がうまいね!」
頬が触れるくらいに顔を近づけて、わたしの描いた似顔絵をじっと見ながら直美おばさんが声を掛けてくれる。
おじさんの親、わたしのおじいちゃん、おばあちゃんと一緒に暮らしている直美さんの家に、毎年お正月に親戚が集まることが、わたし達家族の過ごし方だ。
4人兄弟のお父さんの親戚が全員この家に集まってくる。遠い人はわざわざ飛行機に乗って福岡から神奈川まで来ているのだから、本当に中の良いんだと思う。
酔っ払ったおじさんたちは嫌だから側にいたくないし、一緒に遊んでくれる同年代の子もいない、お母さんは直美おばさんの手伝いで台所とみんながいるこのリビングを行ったり来たりしているから、わたしのこの家での過ごし方は一人で絵を描くことと決まっている。
誰も見ていないテレビからは、なんとか酔っ払ったおじさんたちにも届けようと、一生懸命になっているアナウンサーが駅伝を実況しているけど、お酒の力には勝てないみたい。
”上司がどうした”、”選挙がどうだった”、”最近体が痛い”
毎年同じ話をしているみたいだけど、よく飽きないなと感心する。
顔を真っ赤にして、おじさんたちの話を聞きながらニコニコしているおじいちゃんの顔を描いてみる。
毎年描いているからか、おじいちゃんが歳をとっていることもなんとなく分かる。
シワの数が増えたり、目尻が下がったり、髪の毛を描く時間が減ったり。
「チカちゃんは絵がうまいね!」直美おばさんは一人で過ごすわたしに声をかけてくれる。
「去年よりもまた上手になったんじゃない?今度おばさんのことも描いてね!」
あぁ、確かに直美おばさんは今まで一度も描いたことがなかった。
ずっと台所に立って料理を作り、熱々の出来たてをみんなに用意してくれている。わたしが食べたいと言ったものは魔法のように出てくるし、たまにこっちに来たと思ったら、おじいちゃんにお酒をついでまた台所に戻っていく。
『きっとお母さんには出来ないな…』
子供ながらに、1日でもこんな日があったらお母さんはお父さんとケンカするだろう。
だからきっと、わたしにも出来ないと思う。
わたしに声をかけてくれた直美おばさんは、笑いながらおじさんたちの会話にひとことふたこと話をして、また台所に戻っていった。
19時を過ぎた頃、3人のおじさんたちとその家族はそれぞれの家に帰り、わたし達家族だけが残っている。
これも家が近いわたし達家族の過ごし方だ。
「今日も大変だったね」
わたしの正面に座った直美おばさんに声をかける。
「1年に1回のお祭りだからね。大変じゃないと寂しいの」
「でもおばさんばっかり、嫌じゃないの?」
「チカちゃんのお母さんも手伝ってくれるし、おじさんたちも気を使ってくれてるのよ」
「わたしには全然見えないけど…」
「そう?おばさんには伝わってるからいいの」
「それなら良いけど…」
「それはそうと、約束。お願いできる?」
「約束?」
「お昼にしたじゃない!おばさんの似顔絵描いて」
「あぁ!今からでいいの?」
「お願いします」
直美おばさんは軽く会釈をし、笑顔をよこした。
『あぁ、この人は本当に笑って過ごしているんだ』
直美おばさんの顔をじっと見ながら1本1本線を走らせていくと、可愛らしい顔にシワが刻まれていることに気づく。
目尻に細かなシワがたくさんあり、頬がグッと上がっている。メガネ越しに細くなった目から見える瞳は、キラキラと輝いていた。
「おばさんはずっと家に居て、おじいちゃんのこととか、おばあちゃんのこととか、大変じゃないの?」
紙の上を走るえんぴつの音だけが聞こえていた時間をわたしの声が遮る。
「大変なのかなぁ?あんまり思ったことはないわ」
笑顔でこちらを見つめる直美おばさんの口角がさらに上がる。
お母さんは外で働いていて、そこの友だちと出かけたり、おしゃべりをしているみたいだから、なんだかんだ息抜きができているみたい。だけど、直美おばさんはずっと家に居て、お家のことを1人でしているから、やりたいことが出来ず窮屈そうに見えていた。
「おばさんはやりたいことしてるの?」
なんだか直美おばさんのことをもっと知りたくなって、どんどんと質問をしてしまう。
「やりたいことか…してるわよ!」
「え?ずっと家にいるのに?」
「うん。ずっと家にいるのに」
優しく、ゆっくりとわたしの言葉を直美おばさんは繰り返した。
「おばさんはね、”誰かの役に立ちたい!”って思って、看護師さんになったの。すごく忙しかったし、普通のお仕事の人にはなかなかないようなとても悲しい場面に、とても沢山立ち会うことになるから、辛いこともたくさんあったけど、それでも元気になって、その人の日常に戻っていく姿を見ると、”おばさんも少しは役に立てたかな!”って思えて、とても楽しかったの」
まるで絵本を読むかのように話し始めた直美おばさんの声に、膝の上で包み込まれているようなぬくもりを感じる。
「その病院におじさんが運ばれてきてね。盲腸だったの。手術して少し入院することになったらそこでおじさんと知り合って、結婚することになったの」
「ちょっと昔は古い時代だったから、結婚して、看護師の仕事を辞めて、このお家のことに専念することになったのね」
「正直に言うと初めは楽しくなかったな。早紀と雄也が生まれて、子育てとお家のことで一杯一杯だったからね。あっという間に時間だけが過ぎていって、楽しいって感じる暇が無かったのかもしれないかな」
振り返りながら話す直美おばさんの顔は、それでも笑顔じゃ無くなる瞬間はなかった。
「それでもね。おじいちゃんもおばあちゃんもまだまだ元気で、おじさんも元気にお仕事がんばってくれていて、早紀も雄也も1人前にお仕事できるまで育てることが出来たでしょ」
「わたしが”大切にしたい!”っ想う人に、1番役に立てたのは自慢じゃないけど”わたし”って思えるの。これって特別なことだなって」
子供でも分かる。『ちゃんと幸せを見つけられたんだ』って。
だから直美おばさんはいつも笑顔なんだって。
「どう?できた?」
直美おばさんがわたしのノートをのぞき込んでくる。
すっかり話に夢中になっていたわたしのえんぴつはあと少しのところで止まっていた。
「あら、あと少し。ごめんね。おばさん動いちゃった。また座るから完成よろしくね!」
ピンっと背筋を伸ばし全く同じ位置に座った直美おばさんは、変わらず笑顔をこちらによこしている。
***
”次は〜渋谷〜〜渋谷〜〜〜”
車内に車掌の声が響く。
沢山の人が降りるこの駅では、沢山の人がそれぞれの日常に消えていく。
きっとまた明日、この場所で会えると思う名前も知らない人達だけど、この人達は幸せを見つけているのだろうか。
余計なお世話かもしれないけど、今日、今は気になって仕方がない。
「あなたは、どう?」
誰かに声をかけられた気がする。
『わたしは、どう?』
あの頃のわたしに声をかけられた気がする。
イヤホンから届けられる歌に背中を押される。
『本当の自分出会えた気がしたんだ』
私の幸せは、確かに私の中にあった。
環境のせい。世の中の当たり前のせい。創り上げた正義のせい。
探せば言い訳なんていくらでも見つかるけど、本当は何がいけなかったかなんてもう分かっている。
『大丈夫 行こう あとは楽しむだけだ』
群青 〜YOASOBI〜
2021.05.18
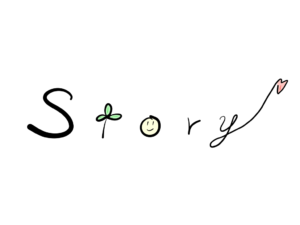
コメント